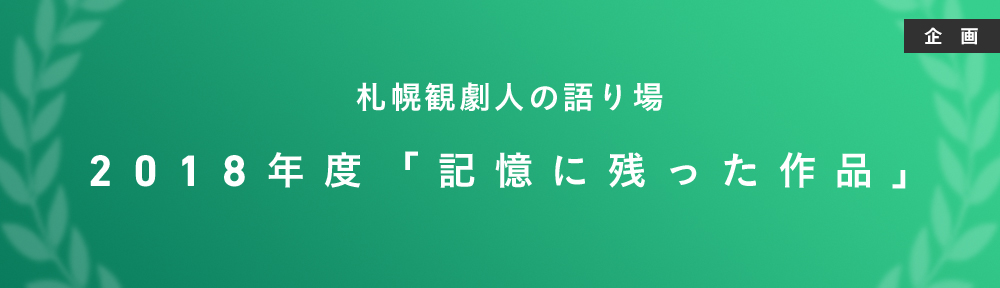
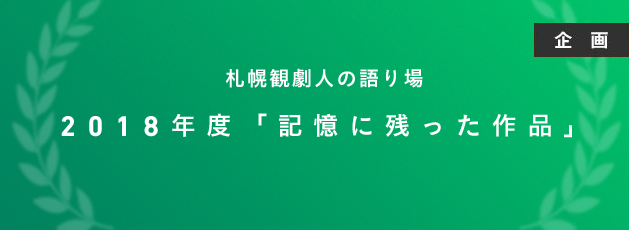
作品が舞台上で輝くのは、ほんのひととき。
けれど観た人の心に強く長く刻まれる光があります。
2018年度の観劇を振り返り、記憶に残った1〜3作品を選んで語ってもらいました。
byうめ
■ 弦巻楽団『センチメンタル』
■ 柴田智之一人芝居『寿』
by九十八坊(orb)
by有田英宗(ゲスト投稿)
■ hitaruオープニングシリーズ『ゴドーを待ちながら』
■ 指輪ホテル『バタイユのバスローブ』
byわたなべひろみ(ひよひよ)(ゲスト投稿)
■関連記事 【企画】2017年度「記憶に残った作品」
うめの選んだ1作品

1.iaku『粛々と運針』 2018年6月 シアターZOO
「普通ってなんだろう」と、考えながら観た作品。
全員共通の“普通”なんて無いことは勿論分かっていても、そこに人の生死が絡むと相手の“普通”を認められず…。兄弟間・夫婦間、どちらの言い分も一方では正しく、でもお互い譲れない気持ちも理解できる。観劇後も考えさせられたという点で、特に記憶に残った作品でした。視覚的にも綺麗な舞台で、是非また再演してほしいです。
九十八坊(orb)の選んだ3作品

1. プロト・パスプア『分裂と光』 2018年6月 コンカリーニョ
「クラアク芸術堂」から派生した若手ユニットとして、より身軽(気軽)に実験的な劇作を行うユニットだと捉えていたのだが、主宰の真髄が見られたのはカンパニー本体ではなくこちらの方だった。プロト・パスプアとはこのために作られたのかと思ったほど。2018年のマイベストとも言える作品。ぜひ再演を。
2. 弦巻楽団#31『センチメンタル』 2018年8月 サンピアザ劇場
これは僕的には初見だが再演であり、戯曲の完成度という点ではこの年度に拝見した同劇団の別の作品の方が上かもしれないのだが、観劇しながら自分の「人生」を顧みるというか、ひどく個人的な思索にふけるという貴重な(奇妙な)時間を貰えた作品。「観劇とは個人的な『出会い』である」という僕の信条からいえばこんな素敵な出会いはめったにない。
3. 柴田智之一人芝居『寿』 2019年1月 BLOCH
2016年に拝見した時とは別モノに見えた。前回はただただ圧倒された舞踏も、今回は一人芝居とパートと違和感なく静かに融合しているという感じだった。完成度と簡単に言ってしまえばそれまでだが、表現者が積み重ねた年月や、観る側(自分)のコンディションなど、いくつもの条件下ではじめて成立する「素敵な時間」だったと思う。
小針幸弘の選んだ3作品

1.イレブンナイン『12人の怒れる男』 2018年8月 かでる2.7
何度見ても発見があって飽きない。陪審員番号10番の不快さに、何が彼をそうさせているのかを考えたくなり、そのうち警察・検察を含めた捜査当局自体が、意識しているかどうかは分からないけど、彼と同じように「あんな連中」として被害者や被疑者を扱っているように思えてくる。エンターテインメントとして面白いし、描かれていない裏も考えたくなる作品でした。
→感想記事はこちら
2.気まぐれポニーテール『アピカのお城』 2018年8月 BLOCH
実は初演の時は、それほど気になるようなものでは無かったのですが、今回は何故か大ハマりしてしまいました。12人~とかぶっていなかったら、毎日通っていたかも。上演版をテレビシリーズのダイジェストと設定して、架空のテレビシリーズを妄想したり、終演後も自分の中でかなりの間楽しめた作品。
→感想記事はこちら
3.コンカリーニョプロデュース『親の顔が見たい』 2019年2月 コンカリーニョ
話の内容というか、描かれていることは、出来れば見聞きしたくないことなのだけど、それがエンターテインメントに仕上がっていて、この芝居の後を考えたくなる作品。会議で何かの決定をした直後に、それを覆す事実が明らかになるという繰り返しは、テーマが軽いものならば、完全にコメディのパターンですよね。正統派の大人チームと部活での上演みたいにも見える中高生チームの違いも面白かった。
納谷さん演出作が2本となりました。理由は説明出来ないけど、どちらも初演で見た時よりも面白かったような印象があります。そのために工夫しているんだから当たり前と怒られそうですが。
3本とも演劇シーズンからとなりましたが、実は最近観たポケット企画なんかも少し気になっています。
島崎町の選んだ3作品

1.アルカス演劇さーくる×吟ムツの会『マグノリアの花たち』 2018年9月 ことにパトス
佐世保の演劇人と札幌の演劇人が共同して作った作品。佐世保チームと演出家は、1ヶ月間札幌に滞在し、札幌チームと舞台を作りあげた。公演は9月末に札幌、10月に佐世保で行われた。お芝居自体のできもよく、心に残ったけれど、その周囲もまたよかった。会場ロビーでは佐世保の名産が売られ、パンフレットには観光案内が挟まっていた。お芝居を通じた地域交流もいいかもしれない。この劇にふれたせいだろう、僕は今年、佐世保への旅を計画している(航空券はもう買った)。
→感想記事はこちら
2.MAM『父と暮せば』 2019年1月 シアターZOO
井上ひさしの著名な戯曲。タイトルは知っていたけれど、初観劇、涙が出た。面白い戯曲を使えば面白い舞台ができる、というわけではない。その本に向きあい、格闘し、表現しなければならない。生半可な態度ではすぐにボロが出る。脚本に喰われてしまう。ましてや「広島」「原爆」を描いた作品だ。覚悟がいる。だけどこの舞台は、成し遂げた。それにしても、1948年を舞台にした20年以上前の戯曲が確実に、いまを照らしている。普遍的ということは、こういうことなんだろう。
3.コンカリーニョプロデュース『親の顔が見たい』 2019年2月 コンカリーニョ
大人チームと中高生チーム、どちらもよかった。それぞれ単独の公演だったとしても、年度ベスト3に選んでいたと思う。大人チームのクオリティはすごかった。とにかく、いいものを絶対に面白く観せる、そういう信念が感じられた。これだけのものはなかなか観られないと思う。中高生チームの、ひたむきに舞台に向きあう姿勢にも心打たれた。なにかを必死にやることによって、純粋さが生まれるんだと、あらためて思った。そうしてこの2つを見比べることによって、観客はより深く、テーマへと潜っていける。良企画だった。
しのぴーの選んだ2作品

1. コンカリーニョプロデュース『親の顔が見たい』(中高生チームバージョン) 2019年2月 コンカリーニョ
テレビドラマも同じだと思うけれど、本(戯曲)は作品の仕上がりに決定的な役割を果たす。演出家でも、俳優でもない。やはり本があっての芝居だと改めて感じた。観客の心を深く揺さぶる畑澤聖悟の本が秀逸である。畑澤は青森県を拠点に活躍する劇作家・演出家で、劇団渡辺源四郎商店を主宰している現役の高校教諭だ。この創作のもとになったのは2006年に福岡県筑前町で起こったいじめによる中学2年の男子学生の自殺事件だ。この事件は、当時マスコミでも大きく報道された。畑澤の作劇は自責の念すら持たない加害児童たちの酷薄さに向けられているが、大人(親、学校、教師)の立場も揺さぶり、突き崩していく。
初演と同じく、ELEVEN NINEの納谷真大演出の大人チームと、introのイトウワカナ演出の中高生チームの2バージョンで上演された。僕は両方観たのだけれど、中高生チームの初日は、久々にキレキレの上がりだった。彼ら、彼女たちの「リアリティのある心当たり感」に心震えた。観客の記憶にある何気ない学校、教室のざわめきや情景から物語を手繰り寄せてみせたイトウの演出も高く評価したい。大人たちが世間体や責任のなすり合いで無様に争い、本来登場すべき「正義らしきもの」が完膚なきまでに壊れていくのをせせら笑うように、罰からするりと逃げていくかのような子どもたちの残酷さを際立たせていたように思う。僕はこの劇に救いやかすかな希望があるとは思わない。それは大人の勝手なファンタジーだろう。公演の前に酷い出来事があった。千葉県で小学4年生の女児が父親の暴力で殺された事件だ。彼女の必死のSOSは、モンスターペアレントの強面から逃れたかった児相の職員と、夫のDVから保身のために共犯になった母親に抹殺されてしまった。中高生の役者たちにとって、僕たちの世界はそういうものなのだという、肌感覚の近さがまったく大人とは違うのだろう。どこか心当たりがあるのだ。だから、大人チームのパフォーマンスを圧倒していたのだと思う。この芝居はこれからも大人チームと中高生チームの2バージョンでぜひ観客に見せてほしい。国境を超えるナラティブがある。優れた演出家と役者たちによってもっと成長させてほしいと願ってやまない作品だ。
2. hitaruオープニングシリーズ『ゴドーを待ちながら』 2018年12月 hitaruクリエイティブスタジオ
札幌文化芸術劇場(hitaru)オープニングシリーズのこけら落とし公演としてクリエイティブシアターで上演されたこの作品。演劇の世界的遺産というべきサミュエル・ベケットの名作をチョイスした斎藤歩の狙いやいかに。「今日は来ないが明日は来る」というゴドーを延々の待ち続ける2人の男の物語。そもそもゴドーは何者なのか。芝居では一切語られることはない。色々な解説本があるが、ゴッド(神)、救世主、メサイヤ、という解釈もあるそうだ。そりゃそうだ。宇多田ヒカルは自死した母に捧げた名曲「道」の中で「人生の岐路に立つ標識はありゃせぬ」と喝破しているが、都合よくゴドーが現れることは誰の人生にもありはしない。誰かに、あるいは何かに救いを求めながらよれよれと生きるしかないのだ。今日も明日も変わらない日常を。
『ゴドーを待ちながら』はそもそも、その演出家バージョンのように思われ、どこが原作に忠実で、どこが原作から逸脱しているのか、例によってアドリブも多々あり、大学時代に読んだ原作などとっくに忘れている浅学な分際では分からない。でも、そこが不条理劇の面白さ、醍醐味といえよう。つまり、いかに人間が不確かな存在であるのか、そもそも私たちは何者で、どこから来てどこへ行くのか。普段絶対に考えないことを、芝居を観ながら考えている自分がいた。時代と対峙しながら時代精神の中で問いかけること。畢竟、それは演劇の役割に他ならないだろう。クリエイティブシアターとのサイズ感も良く、島次郎の舞台美術に感嘆。大野道乃による照明プランも美しい。衣装(磯貝圭子)も世界観にマッチしていた。東京からの客演、福士惠二、高田恵篤が圧巻の存在感!この二人を観ただけでも十分お腹一杯。面倒な作品世界を素晴らしく魅力的に観客に提示してみせた斎藤の演劇頭脳に改めて敬服した。
中脇まりやの選んだ3作品

1. intro 『こっちにくるとあの景色がみえるわ』 2018年5月 シアターZOO
introがすきなので、introは何度でも見たい!introの舞台はセリフ、動作、すべてがリズムから成り立つと思う。グルーヴに近い。それから独特な俳優陣たち。そしてそれが癖になってしまう。もう虜です。アパートの一室の空き室でサンバのリズムとともに湧き出るゴミ。そして作り出されるゴミの海。そこはあの世かこの世か。見るたびに発見があるのでは、と思う。
→感想記事はこちら
2. 東京芸術劇場ルーツ企画『書を捨てよ町に出よう』 藤田貴大演出 2018年11月 教文大ホール
開演前のBGMのセンスのよさから圧倒され、宇野亜喜良のポスターにほくそえみ、単管が組み立てられ、移動していく様や注目のミナペルホネンの衣装も面白く、噂にきく解剖シーンを目撃する。もはやお話の良し悪しはわからなくなってしまうのだけど、ひとつひとつのことにエッジが効いていて、刺激が強い。そして、主人公ひみくんが絶妙な塩梅でした。
3. 空宙空地『轟音、つぶやくよう うたう、うたう彼女は』 2018年11月 コンカリーニョ
個人的なテーマでもある「母と娘」にがっちりとはまってしまい、終演後に涙が止まらなくなってしまった。これは非常に困った。生きることに対しての諦めと、静かな肯定を感じた。若いときには見えなかった諸々も、年を経れば、苦労をすれば、見えるようになってくる。「なんにもわかってなかった」とわかる頃には時すでに遅し。もう一度見たらどんな気持ちになるか、できることなら確かめたい。
マサコさんの選んだ2作品

1.さんぴん『NEW HERO〜突撃!隣のプレシャスご飯、デリシャス!!〜』 2018年10日 よりiどこオノベカ
男子4人の、「楽しんで作った」感が満載の舞台。各々のスキルの高さ、ぐぐっと押し寄せてくるような圧力の高さなどなど、あらゆる点で「見なきゃ損だな!」と思った。来年の札幌国際芸術祭に参加したらいいのにな、と勝手に期待。
2.高校演劇全般
根室高の抜群の破壊力や、卒業公演で「ラブストーリー」として完結した新篠津高等養護など、2校に限らず強く印象に残る作品が多かった。今年の各支部大会でどんな作品が出てくるのか超楽しみ。現在、今年の春フェス参加校の映像が観られるようですよ(https://freshlive.tv/kouenkyo/programs/archive?sortType=endAt)。北海道代表は、〝山崎サンセット〟の大麻『Cavatina』です。
瞑想子の選んだ3作品

1. やまびこ座30周年記念・野外巨大人形劇『テンペスト』 2018年8月 やまびこ座
ノリの悪いタイプの大人(私)も気が付けば楽しんでいた観客参加型作品。シェイクスピアの『テンペスト』をベースに、沢則行が演出・美術を担当。
エアリエルが案内するアトラクションツアーの趣向で、客は劇場内外を巡り歩いて物語を目撃し、ラストは野外で、屋上に登場する巨大な人形を見上げる。美術も人形もほぼ段ボール製なのにしっかりアート(かつ学園祭っぽい楽しさ)。
出演者は子どもも若者も一生懸命、ベテランが要所を押さえ、統括者のセンス良さと構えの大きさが観客をきちんともてなしてくれた。絆は感じるのに内輪ノリがなく、開かれていた。
劇場が30年で培ってきた人脈・人材・ノウハウ、地域で果たしている役割をもみせてくれた作品だった。
2. ヨーロッパ企画『サマータイムマシン・ブルース』『サマータイムマシン・ワンスモア』 2018年11月 道新ホール
ドタバタ入れ替わりモノでは、その忙しさで役者が素笑いしたり、客と馴れ合って笑いにしたり…というものを多くみかけるが、全くそんな気配がなかった。素晴らしい。
『〜ブルース』は、場面に効かせる笑いが優勢かつ序盤が重いと感じたが、「使い古されたタイムマシンものでこのアイデアはいいなぁ!」という強烈なのが2つあり(パラドックスの掟の破り方があっぱれ)、言葉で効かせる笑いもいくつかあって、全体として満足した。
『〜ワンスモア』は、脚本がより緻密で伏線だらけ。人物に彫りがみえ「なるほど大学を出て社会人になったのだなぁ」という物語の幅があり、「あまちゃん」ばりに年代ネタをぶっこんである。笑いの大部分が「筋の展開上の必然を持った笑い」だったことも好み。ズレ、ギャップ、繰り返しのほとんどが脚本上のもので、場面にしか効かない笑いはあまりなかった。
ブルースがアイデアとセンスの作品なら、ワンスモアは計算と技巧が効いた手練れの作品、と感じた。特段中身はないエンタメだが、筋の運びとひねりが最大の楽しみどころの作品のように思う。スカッと楽しかった。
3. hitaruオープニングシリーズ『ゴドーを待ちながら』 2018年12月 hitaruクリエイティブスタジオ ※初日観劇
凄い脚本だ。描かれているのはまさに「私たち」。何かが起きているようで起こらない日々、状況に対する無力、様々な感情の果てに訪れる慣れ、惰性、薄らぼんやりとなっている希望、既に費えつつある渇望。哀れで滑稽で不遜で無様な登場人物4名はいずれも私だった。
シンプルながら広がりを感じさせる舞台美術、そこにいる斎藤歩は惨めでくたびれたエストラゴンの身体そのものだった。札幌の舞台で、照れたり斜に構えたりしたところのない役そのものの斎藤を初めてみたように思う。感動した。が、後半のアドリブが始まるといつもの身体に戻ってしまった。残念。
ゴドーは改変が許されないと聞くが、この上演ではどうだったのか。日本での他例でもアドリブは割と多く、漫才バリの笑いを良しとする意見もあるようだ。串田和美演出では緒形拳が「なんとか大衆演劇にしたかった」と言ったというテキストをみかけた。なぜ? こんなにも普遍的な名作を大衆演劇にする必要があるのか? 「いま・ここ」に着地する方法はそれしかないのか? 演劇が芸術であるというのなら、ご当地ネタの笑いなど入れずに演じてみせてほしかった。客が退屈するならそれも脚本家の意図という可能性もあるだろう。
劇場のオープニングシリーズ、名高い不条理劇脚本、迫力の舞台美術、東京からの強力な助っ人俳優。(哀しみと表裏の笑いが必ず生じるとは思うが)ひとかけらも笑えずわけがわからなかったとしても、客は必ず何かを持ち帰ったはずだ。演出家にとって、演劇と客を信じてみる絶好の機会であっただろうに。観てみたかった。
やすみんの選んだ3作品

1. 『民衆の敵』イプセン作 ジョナサン・マンビィ演出 シアターコクーン・オンレパートリー 2018年12月1日 シアターコクーン
一昨年の「るつぼ」に続き、マンビィx堤真一の作品。前回同様、人間いかに生きるか、というテーマがありながら、何よりも「民衆」の怖さ、「正義」の苦しさを感じた一品。ストーリー的には、内部告発者が社内で憎まれる成り行きが、町ぐるみで起こると考えればよいかと。堤真一、段田安則、外山誠二らが安定して見せる演技はさすが。しかし凄いのは、第2の主役とも言える「市民」役の一団だ。子役から年配者まで老若男女様々な市民が、時に群舞のようなパフォーマンスを披露しながら登場する。そして感心するのは、集団としてとらえられるこの25名からなる「市民」一人一人に名前があり、職業があり、性格の特徴があり、個々の登場人物としているイプセンの視点である。市民Aや漁師、という役名ではなく、ちゃんと名前がある。市民、民衆とは、得体の知れない漠然としたものではない、そういう個人からなる集団なのだと今更ながらに思い知る。昨今のSNS炎上などは、姿も見えず一層不気味ではあるが、個々の個人の仕業には違いない。主人公トマス・ストックマンに対する憎しみが民衆に芽生える瞬間を、舞台に敷き詰められた石を拾い(舞台上にはいないトマスの後ろ姿に向かって)投げつける動作で表現していたのが、人間の闇の立ち上がりを見るようでゾッとした。最初に石を拾ってなげたのは、若い男でも酔ったオヤジでもなく、上品そうな老婦人だったのは心憎い演出だった。
2. 『出口なし』サルトル作 小川絵梨子演出 シス・カンパニー 2018年9月15日 新国立劇場 小劇場
大竹しのぶ、多部未華子、段田安則による密室劇。「地獄」という設定の鏡のない部屋。何やら罪を犯したらしい互いに見知らぬ3人。「地獄とは他人だ」の名言を残したサルトル。自分という存在は他人を通してしか認知できない。違うの、私はそんなんじゃない、誤解だ、と叫んでも虚しい。鏡がなければ、私ってきれい?と他人に問うて反応を見るしかない。では「自分は自分だ」と他人と関わらず生きていくか。はて、そうもできない人間たちを、皮肉、ユーモア、憐憫、愛情で描く、なんだかオシャレな一品。3人いると必ず2対1になる、とは、アメリカのある学長さんも学生寮の部屋割りについて言っておられた。劇ではそのバランスシフトが面白い。
3. 空宙空地『轟音、つぶやくよううたう、うたう彼女は』 関戸哲也演出 2018年11月 コンカリーニョ
観劇後に感想文を揚げたので詳細は割愛。TGRで受賞し、演劇シーズンで再演が決定しているので宣伝をかねて。ベタベタのお涙頂戴にせずさらりと等身大。このタッチが奥深い。なぜか、「キットカットを割らずに食べる女」のくだりも頭に残っている。
※記憶に残るラストシーン特集(そんな企画はない)としては、シアターコクーン、フィリップ・ブリーン演出、三浦春馬主演の『罪と罰』のラストシーン、振り向いた春馬くんが罪を告白するのか、と息を呑んで次の言葉を待つ間に暗転!という「やーん!」という凄まじい余韻を残した瞬間。そして演劇シーズンでの、弦巻楽団『センチメンタル』のラストシーンの主人公による号泣。もう彼のように純なことで泣けない自分の穢れを感じた瞬間。同時にワーズワースの詩「草原の輝き」を言い訳のように思い出した瞬間。ーー草原の輝き、花の栄光、その時間を取り戻すことはできない、だが嘆くことはない、その奥に秘められた力を見い出すのだーー。昨年はこの同じフレーズを、藤田貴大演出の寺山修司『書を捨てよ、町に出よう』でも思い出した。寺山の生きた昭和。「あの時代」は戻らない。しかし残された力は、姿形を変えて存在する。まもなく平成も終わる。平成から我々は何を見い出すだろう。
→感想記事はこちら
有田英宗(ゲスト投稿)の選んだ1作品
![]()
1. tattプロデュース『命を弄ぶ男ふたり』 2019年3月 シアターZOO
自殺願望の男ふたりが鉄路へ飛び込む場所を物色中に出会って、減らず口をたたきあう悲喜劇。
顔中包帯の男(納谷真大)と眼鏡の男(斎藤歩)はともに結婚や色恋など、女性を巡って思い詰めている。
深刻さを競い合って滑稽だった。真面目さも過ぎるとおかしみと背中合わせになるのは日常よくある風景だ。
そしてその先、漂着するのは生の悲哀の海岸だ。重いテーマをふたりが軽やかに演じて面白かった。
熊喰人(ゲスト投稿)の選んだ3作品
![]()
1. イレブンナイン『12人の怒れる男』 2018年8月 かでるホール
イレブンナイン版『12人の怒れる男』は2015年8月以来2度目の観劇。原作が良くて、脚本が良くて、キャストが良ければ、何度観ても感動し考えさせられる作品。河野さんや平塚さんの演技の熱演に魅了された2時間だった。
2. アルカス演劇サークル×吟ムツの会『マグノリアの花たち』 2018年9月 ことにPATOS
こちらの作品もストーリーが良く、脚本が良かったので楽しめた作品。舞台はアメリカなれど、そこで交わされる会話は昭和時代の井戸端会議。淡々と過ぎる日常の中でのちょっとしたアクシデント。出演者全員が役回りを見事に演じていた。怪優ナガムツさんの好演に拍手。
→感想記事はこちら
3. yhs『白浪っ!』 2019年2月 コンカリーニョ
2017年度のTGR札幌劇場祭で大賞を受賞した作品のリメイク。設定やストーリーにやや無理があったが演出のうまさと舞台の使い方のうまさが光った作品。17名もの役者さんを使い、それぞれに個性溢れる人物に仕立て上げた南参さんに拍手。
S・T(ゲスト投稿)の選んだ3作品
![]()
1. 劇団怪獣無法地帯『月見草珈琲店~まてば甘露の日和あり~』 2018年6~7月 ことにパトス
幻想的なシーンでボクは不思議な感じを抱いた。当たり前の話し観客の一人として自分は観ているのだが、他の観客の頭を眺めながら「観客も含めて作品?」と思ったのだ(役者が観客席に出てきた訳では無い)。登場人物の人生を皆で見守るような感覚で、「観客の中の一人」であることを嬉しく思えた。作・演出の伊藤樹、恐るべし。
→感想記事はこちら
2. 演劇家族スイートホーム『裸足でベーラン』 2018年11月 BLOCH
TGR新人賞受賞作品。賞を争うであろう他の1作品も観ていたので、新人賞受賞には納得。何と言ってもクライマックス、ありふれた一言で劇場の空気を変えたのが印象的。今作は高橋正子さんの脚本だが、スイートホームのホームページを見ると他のメンバーも脚本を書くようだ。札幌に限らないのかもしれないが、個人的には役者に比べ劇作家の数が少なすぎるように感じている。スイートホームは、そういう意味でも今後に期待できるカンパニー、だと思っている。
→感想記事はこちら
3. 北海学園大学演劇研究会 卒業公演『いつかの日曜日』 2019年2月 BLOCH
泣いた。ボクが一番泣いた映画は「レナードの朝」、美しいダンスシーンに涙した。それに負けないくらい、終盤の山崎拓未さん(演劇家族スイートホーム)と簗田愛美さんのシーンは美しかった。劇場からの帰り道も涙が止まらなかった。魂の存在の有無、脳に記憶することと魂に記憶することに違いはあるのか?考えさせられる作品でした。脚本・演出は福田倫久さん。また作品を観ることはできるのだろうか?
※2016年3月、ボクは初めて演劇を観ました。数回観て、大げさな話「ボクの人生に演劇は必要無いな」と結論付けました。けれど音楽を聴きに行ったイベントで予想外の出会いがあり、観劇を続け2018年は「札幌観劇人の語り場」へ投稿までしてしまいました。人生とは不思議なものですね。昨年度は再観を入れても10回くらいしか観ていないと思います。ツイッターをみると、ボクより多く観劇されている方は沢山いらっしゃるようですので、気軽に語り場さんに投稿してみてはいかがでしょうか?ボクは遅筆ですし書きたくなった作品の感想だけ、ゆるく投稿を続けていけたら・・・、と思っております。
わたなべひろみ(ひよひよ)(ゲスト投稿)の選んだ3作品
![]()
1. コンカリーニョプロデュース『親の顔が見たい』 2019年2月 コンカリーニョ
いじめをテーマとした重く、出口のないテーマを大人チームと中高生チームとで公演。
大人チームは異様なほどの緊張感で、とことんリアルに親のエゴを演じる。感情のほとばしる様は迫力があり、舞台で展開される物語が終わっても、そこにいた人たちには、これから長い苦しみが続くのだと思わせる説得力があった。
対する中高生チームは、制服のような白シャツで子どもの姿のまま、大人を模す。中高生が大人の発する醜い言葉を口にするのを見ると、このセリフを言いながら、この子はどういう感情に揺さぶられているのだろうと動揺する。最後に靴を自分のものに履き替えて、大人の仮面を取った瞬間の笑顔に涙が出た。
全く同じ脚本であるのに、演出、出演者の違いでここまで違うものになるというのが驚きだった。
いずれのチームでも、深く深く心に刺さって、いつまでも抜けないとげを残すような作品だった。
2. hitaruオープニングシリーズ『ゴドーを待ちながら』 2018年12月 hitaruクリエイティブスタジオ
会場を斜めに貫く一本道と裸の樹。島次郎さんデザインの舞台美術が素晴らしかった。
真新しい劇場で不条理劇の代表といわれる作品の上演。ワクワクせずにいられなかった。
「わかろう」として観るのをやめた瞬間、面白くてしかたなくなり、しかし、そのうちに、しんとした気持ちになってきた。
毎日、信じてゴドーを待つ二人の姿が、北海道で演劇文化をしっかりと根付かせようとしている役者自身の姿に重なってきたのだ。繰り返し、繰り返し、良いものを作ろうとする姿。
きっとあの日、また演劇の新しい種がまかれたのだと思う。そして、それはいつか豊かに枝を張る大木になると信じている。
3.指輪ホテル『バタイユのバスローブ』 2019年3月 naebonoアートスタジオ
指輪ホテルの本公演を観るのは初めてだった。普段はアーティストのアトリエであり、ギャラリーとして使われる会場で繰り広げられたのは、夢の中にいるような、妙にリアルなのだけれど、焦点が合わなかったり、辻褄が合わなかったりする世界だった。
観るものではなく、まさに体験するもの。
春先とは思えない寒さの中、時折、外から列車の音が響き、突然、外へとシャッターが開かれ、積み上げられた雪で作られた雪玉が目の前を飛んでいく。
その場では何が起こっているのかわからなかったものが、数日してから意味を持って浮かび上がってきた。体験が寒さと一緒に身体に刻み付けられた証拠だ。
熱烈なファンの多い指輪ホテル。これはクセになるかも。
■関連記事
【企画】2017年度「記憶に残った作品」
text by 札幌観劇人